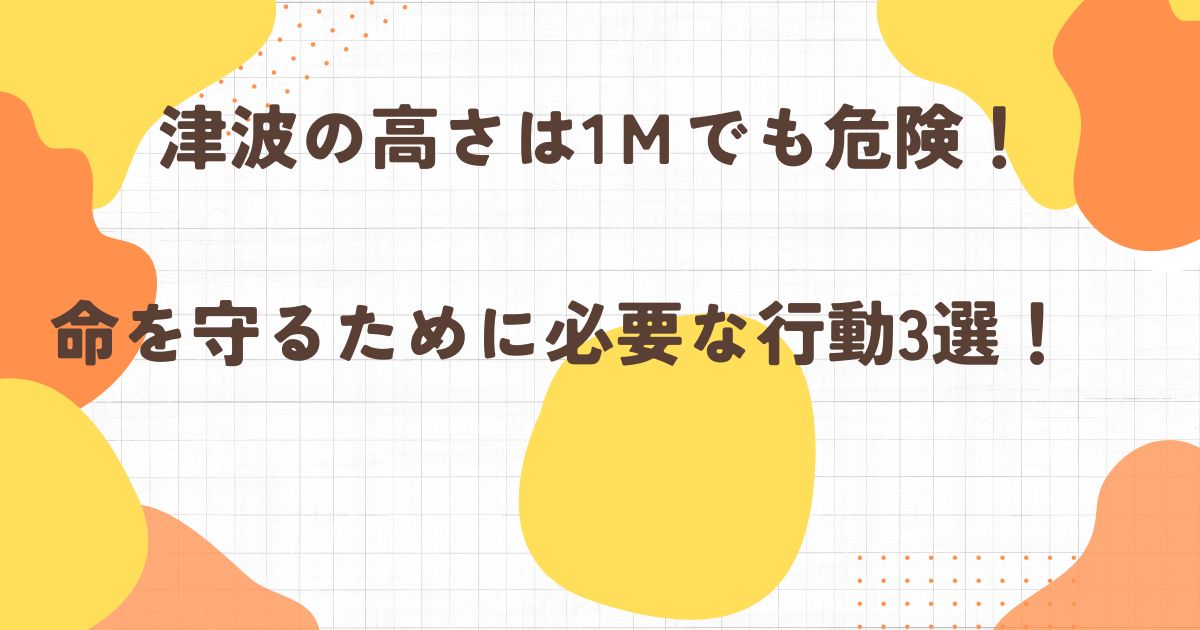7月30日午前8時25分頃、カムチャツカ半島付近でマグニチュード8.0(その後8.7に修正)の非常に大きな地震が発生しました。
この影響を受け、同日8時37分には、日本にも高さ1mとなる津波到達の警報が発令されています。(後に最大3mと修正)
この記事では、現在発令中の津波警報において「津波の高さ1m」がどれほど危険であるか、そして皆さんがご自身の命を守るために取るべき行動について詳しくお伝えします。何よりも人命を最優先し、適切な行動を選択してください。
津波の高さが1mになるとどれだけ危険か
わずか数十センチでも津波は脅威となる
1mの津波は車が流されるほど危険です。
津波の恐ろしさは、見た目の高さだけでは測れません。内閣府の分析によると、津波1メートルに巻き込まれれば、ほぼ死亡するとされています。
なぜなら、津波は「海水全体が塊となって」普段とは違う波となって、陸に押し寄せるからです。
例えば、わずか30cmの津波でも車やコンテナを浮かせます。
50cmから70cmの高さになると、健康な成人でも流されてしまうほどの威力があります。
もし津波が70cmから100cmに達すれば、立っていることはほぼ不可能で、大きな漂流物にぶつかるなど、命を落とす危険性が非常に高くなります。
津波は第2波以降に最大になることも
「津波は1回で終わりではない」という認識が重要です。
津波の怖い点は、一度目の波(第1波)で終わりではないということです。
巨大地震による津波は、複数の波が重なり合いながら何度も押し寄せることがあります。
実際に東日本大震災では、岩手県大船渡市の綾里湾で40.1mもの遡上高が観測された事例があります。

陸に寄せる「押し波」と、破壊された家屋や車を海に引き込む「引き波」が繰り返し発生し、勢いを増しながら巨大な岩や住居すら軽々と流します。
湾や崖など、地形によっては予想される波の高さの最大4倍にもなることもあるのです。
津波1mの過去シミュレーション情報
「海に近い商店街では町の奥まで津波が到達する可能性もある」ことが、鎌倉市で想定された津波のシミュレーションで再現されています。
見慣れた街並みを津波が襲う様子がリアルに描かれており、震源域によっては津波発生から街に到達するまでわずか8分という予測もあります。
この限られた時間での行動が、生死を分けることになります。
例えば、低地の由比ヶ浜や鎌倉駅周辺では、街のかなり奥まで津波が到達すると想定され、一方で七里ヶ浜のように高台が背後にある場合でも、海から高台までは高い石段を登り、国道や江ノ電に注意して移動する必要があります。
腰越商店街のように谷状の低地がある場所では、川に沿って津波が遡上してくるため、川から離れて高台へ避難し、避難方向を示す道路表示に従うことが大切です。

津波1m 被害から学ぶ教訓
「震災の経験から得られる情報は大きい」という点を決して忘れてはなりません。
過去の災害から学ぶことは非常に重要です。
東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県気仙沼市にある宮城県気仙沼向洋高等学校は、津波が4階まで到達しましたが、この学校では職員と生徒全員が無事でした。
これは、全員が協力し、より高い場所へ、一刻も早く逃げ切れたからだと考えられます。
東日本大震災から時間が経ち、報道が減ったことで復興が進んでいるように感じるかもしれませが、津波が襲った地域には、いまだに工事中の場所や住宅地跡が更地のまま残るなど、当時の爪痕が色濃く残っているのが現状です。
津波の高さ1mから命を守る方法
方法① 津波てんでんこ:避難行動の原則
津波から命を守る教えとして、「津波てんでんこ」という言葉があります。
「てんでんこ」とは方言で「各自」「それぞれ」という意味です。
これは、「津波が来たら各自で逃げなさい」という教えで、岩手県釜石市の児童・生徒の99.8%が助かった「釜石の奇跡」として広く知られるようになりました。
具体的には、海岸付近で地震を感じたら、津波から身を守ることを最優先に考え、誰の指示も待たずに自分で判断して行動することです。
家族の安否を気遣う気持ちは当然ですが、まずは各自が一刻も早くできる限りの高台へ逃げ、自分の命を守ることが大切です。

先の大震災では、家族を心配して海沿いに戻ったり、津波の専門家ではない学校や会社の指示を優先したりしたことで犠牲になった命も少なくありません。
緊急時には、お互いにまず自分の身を守る約束や、連絡が取れない場合の集合場所などをあらかじめ決めておくことが重要です。
方法➁ 命を守る「UITEMATE」の救助方法
万が一、海に落ちてしまった場合でも、命を守るための救助方法があります。
それが「UITEMATE(浮いて待て)」です。

東日本大震災の際にこの方法で助かった子どもがいることで有名になりました。
助けを求めようと体が縦になると溺れてしまう危険があります。
この方法は、肩まで腕を開いて浮きやすい体勢を作り、衣服や靴を身に付けたままにして浮具代わりにすると、呼吸を確保することができます。
漂流物がある場合は難しいかもしれませんが、こうした知識もいざという時に役立つでしょう。
方法➂ 津波から避難する時の注意点
津波発生時、最も重要なのは、以下の点を心掛けることです。
- 一刻も早く安全な場所に避難する
- 迷わず高台に逃げる選択肢を選ぶ
- できる限り海から離れること
- 高台がない場合は、鉄筋コンクリート造りや鉄骨造りの高い建物を目指す
- 避難時に車は使わないこと
- 川も危険。水辺には近づかないこと
海沿いにいる場合は、事前に津波避難所を確認しておくことが不可欠です。

非難は車を使用せず、徒歩での避難が原則です。車移動では、渋滞に巻き込まれる可能性もあり、津波にのまれた場合、現在の車のほとんどは水圧でドアが開かなくなり、パワーウィンドウも内側から開かず、脱出が非常に困難になります。
渋滞に巻き込まれそうであれば、キーを付けたまま路肩に駐車し、すぐに車を降りて徒歩で避難することを強くおすすめします。
そして、避難時には海だけでなく、川にも絶対に近づかないでください。
津波は川を遡上する性質があるため、非常に危険です。
2016年11月22日に発生した地震では、宮城県多賀城市を流れる砂押川の水が逆流する様子が撮影されており、このような勢いの水に近づくことは、命に関わる行為です。
油断せず、常に備える心構え
「災害時の対応を心のどこかで準備しておく」ことが大切です。
頻繁に地震が起こる日本において、最も怖いことの一つは、災害に対する「慣れ」が生じてしまうことです。
「今度も大したことないだろう」という油断は、大きな危険につながります。
これまでの経験に照らし合わせることなく、常に最悪の事態を想定し、疑うことをやめない心構えが大切です。
自然に「まさか」は通用しません。いざという時には、最後まで諦めずに自分の身を守る行動を取りましょう。
津波は、最初に引き波が来ると考えられがちですが、これは必ずしも当てはまりません。
引き波が起こらずに、いきなり押し波が来る場合もあります。
また、日本の地震だけでなく、海外での大地震が原因で津波が押し寄せることもあります。
津波注意報や警報には十分な注意が必要です。
わずか数十センチの津波でも成人を簡単に流してしまうほどの威力があることを決して忘れずに、いつどこで起こるかわからない災害に備えておくことが私たちの命を守るために不可欠です。
記事のまとめ
津波から非難する事になった場合は、何よりも最優先で、ご自身の命を守ること行動を取ってください。
筆者は東日本大震災時に車で神奈川にいて、都内に戻るまで約18時間車で過ごした経験があるので、その時の困難と怖さの経験は今でも胸に刻まれています。
移動できる方は迅速な移動を心がけ、同時に安全な場所を確保できた方は、周囲と情報を共有するようにしましょう。
共有された安全な情報によって、危険な方向に向かう方が少しでも減ることを願っています。
津波から命を守るために、今できる最善の行動をとりましょう。